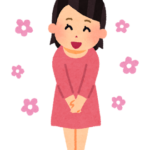この記事を読むと、さ行音の中の「さ・す・せ・そ」音について以下のような内容がわかりますよ。
1 「さ・す・せ・そ」音を発音するとき、口の中の舌はどうなっているか。
2 「さ・す・せ・そ」の発音練習の例
3 「さ・す・せ・そ」音に効果的と思われるお口の体操(あくまで、経験からの私見です。)
ことばの教室の担当の方はもちろん、ご家庭でもさりげなく取り組める方法などをお伝えできればと思います。
1 「さ・す・せ・そ」音の口の中
まず、なぜ「さ・し・す・せ・そ」音ではなく、「さ・す・せ・そ」音なのかお伝えします。それは、「し音」だけ、口の中(舌の位置)が違うからです。「さー」と言ったあとに、「しー」と言ってみてください。舌が少し、口の奥にいきませんか?い音の列の音(き・し・ち…など)は、特別なんです。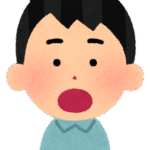
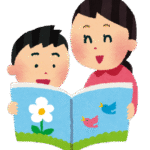
さて、では「さ・す・せ・そ」音を出すときの口の中はどうなっているかというと、「口の中の息が、上歯と舌先との間にできたわずかな隙間を通り、摩擦させて口の外へ出て」います。さ行音のもとの音(子音)で専門用語で無声摩擦音(s)と言います。「わずかな隙間」から「摩擦させて」息を出すから難しい音なんですね。5歳ぐらいまでに完成すると言われますが、7歳前後までと、とらえた方がよいと思います。個人差がありますからね。早いからいいというわけではありません。
発音の順番については、下記の記事をご覧ください。
子どもの発音 どんな音から上手になるのかな? | ことばの教室(ことのはーゆゆ)
それでは、「さ・す・せ・そ」音の舌の位置を確かめてみましょう。「た」と言おうと思って舌を構えてみてください。舌が上歯と口の天井部分(口蓋)の前方についていませんか。上歯に舌をつけたまま、ゆっくりと舌の力を抜くと、それがさ音の舌の位置に近くなります。そのまま、息をゆっくりと出すと、無声摩擦音になります。
「さ・せ・そ」音が「た・て・と」音になっている(置換している)お子さんは、この隙間をつくるのが難しい状態にあると言えます。
2 「さ・す・せ・そ」の発音練習の例
では、ことばの教室では、「さ・す・せ・そ」音をどのように発音練習をしているでしょうか。
発音練習としては、「風の音」、「舌の構え(位置)を教える方法」、「つ音から導く方法」、「キーワード法」などがあります。ここでは、「風の音」と「キーワード法」をお伝えします。
「風の音」
「風の音」は、ストローを使った「風の音(無声摩擦音)」で、す音を導きます。
①ストローを舌の真ん中にそっと置きます。
②舌は出したまま、ストローを舌と一緒にそっと上下の唇ではさみます。
③その状態で息をそっと出します。シューという音が出ます。
④この「シュー」に「ウ」をつけると、す音になります。
ことばの教室では、「風の音」の手本を示して、スモールステップで練習していきます。必ず、①~③を1つずつ十分に正しく行ったあとに④に進みます。「風の音」を実施するにはいくつか注意点があるので、以下のサイトが参考になりますよ。
国立特別支援教育総合研究所ネットで学ぶ発音教室https://forum.nise.go.jp/kotoba/htdocs/?page_id=45
す音から練習するといいことが1つあります。それは、す音にあ音やえ音やお音をつけると、さ音、せ音、そ音を導けるということです。音の足し算ですね。
「キーワード法」
「キーワード法」というのは、「さ・す・せ・そ」音の中で、正しい音が出せる言葉がある場合に使えます。この方法は、他の音の発音練習でも使えます。
①正しく発音できる言葉があったら、それを繰り返し発音します。たとえば、「さとう」だったら、たくさん「さとう」を言います。
②少しずつ、「さとう」の「とう」の部分を消していきます。
③さ音とさ音文字カードをマッチングします。(さ音の意識付けです)
これらの発音練習を、ことばの教室では、絵カードを使ったり、タブレットを使ったりしながら、楽しく行うことがほとんどです。そのお子さんに合わせて行うためです。もちろん、トレーニング色が濃い方が合う場合は、そういう雰囲気で行います。
発音練習と並行して行う練習は、音の聞き分けです。たとえば、「さ音」が「た音」になっている場合は、「さ音」と「た音」を聞き分ける練習をします。
ご家庭では
これらの練習は、ことばの教室の先生にお任せした方がよいと思います。ご家庭では、たくさん正しい「さ・す・せ・そ」音を耳から入れてあげてください。絵本の読み聞かせもいいですね。そして、言葉の「言い直し」はしないでくださいね。発音の獲得には個人差があります。お子さんの伸びる力を信じましょう。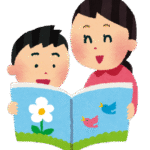
「さ・す・せ・そ」音に効果的と思われるお口の体操
最後に、「さ・す・せ・そ」音に効果的と思われるお口の体操をご紹介します。あくまでも、経験からの私見ですが、参考になさってください。授業は45分間あります。「お口の体操」をしなくても、発音練習はできます。でも、せっかくたっぷりと時間があるのですから、舌の筋力やコントロール力をつけるのはわるくないと思います。それに、「お口の体操」は、お口の準備運動のようなもの。これから、「発音練習するぞー」という動機づけになります。発音がうまくいかない日があっても、「お口の体操」で、たくさん子どもをほめることもできます。ほめると、子どもはもちろんうれしいですが、実は先生も心が弾んでうれしくなりますよ。
舌先を意識しやすい「お口の体操」を集めてみました。
舌ずもう
舌先をまっすぐ口から出して、口の前にあるおせんべいなどを押します。「まっすぐ」がポイントです。ことばの教室では、木製の舌圧子(アイスの平たい棒のような物)を使うこともあります。力がついてくると、おせんべいに穴が開いたりしておもしろいですよ。 

フルフルスポット
舌をまっすぐにしたまま、左右の口角に付けます。リズムのよい「いち、に、いち、に、いち、に、」という言葉に合わせて舌先を左右の口角に付けます。そして、「スポット」と言われたとき、舌先を上の歯の裏の付け根あたり(スポット)に付けます。上手になったら、どんどんリズムを速くします。いつ「スポット」と言われるかわからないので、子どもは楽しみながら「フルフルスポット」に取り組めます。スポットの位置については以下の記事で書いてあります。参考になさってください。
おうちでできるお口の体操 | ことばの教室(ことのはーゆゆ)
舌なめ(リップトレイサー)
上唇を舌先でなめていきます。右から左へ。左から右へ。最初は、速いスピードでもよいですが、少しずつゆっくりできるようにします。10秒でできるようになると、舌のコントロール力がついてきたことになります。


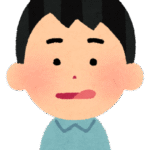
ご家庭では
トレーニングではなく、楽しく取り組めるものがよいと思います。以下の記事を参考になさってください。「噛む」、「うがい」、「歯みがき」は基本です。
おうちでできるお口の体操 | ことばの教室(ことのはーゆゆ)
まとめ
いかがでしたか。「さ・す・せ・そ」音を発音するときの舌の位置やそれに効果がありそうなお口の体操などがお分かりいただけたら幸いです。ことばの教室では、このほかに、音の聞き分けの練習等もして、自分でフィードバックする力も育てます。そうすることで、正しい発音が生活に広がっていきます。
繰り返しになりますが、正しい発音の獲得には個人差があります。気になる場合は、幼稚園や学校の先生に相談なさるとよいと思います。
さて、次回は「気持ちが落ち着かないときの対処法」について考えてみたいと思います。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。ことゆゆでした。