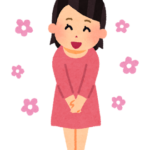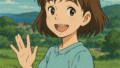この記事を読むと、カ行音について以下のような内容がわかりますよ。
1 カ音を発音するとき、口の中の舌はどうなっているか。
2 カ行音の発音練習の例
3 カ行音に効果的と思われるお口の体操(あくまで、経験からの私見です。)
ことばの教室の担当の方はもちろん、ご家庭でもさりげなく取り組める方法などをお伝えできればと思います。
1 カ音の口の中
さて、「カ音」を出すときの口の中はどうなっているかというと以下のようになります。舌が下がっていて(収まっていて)、舌の奥だけが「か、か、か…」と言うと上下します。カ音のもとの音(子音)は、無声破裂音(k)です。タ音とカ音を交互に発音すると、舌先の位置の違いが分かり、カ音はどっしりと舌が下にあるのが分かります。だから、カ行音は舌の奥を上下して、(軟口蓋と奥舌で)息を破裂させて出す音です。
「軟口蓋とは?」と思った方は、下記のサイトの図でご確認ください。https://forum.nise.go.jp/kotoba/htdocs/?page_id=15
3歳ぐらいで発音ができるようになる音ですが、個人差があります。発音の順番については、下記の記事をご覧ください。
子どもの発音 どんな音から上手になるのかな? | ことばの教室(ことのはーゆゆ)
2 カ行音の発音練習の例
以下のチェックポイント2つは、どの音を発音練習するときにも大切です。
発音練習としては、「舌押さえ法」、「舌の構え(位置)を教える方法」、「ク音から導く方法」、「キーワード法」「ンーガー法」などがあります。ここでは、「舌押さえ法」と「キーワード法」をお伝えします。
「舌押さえ法」
「舌押さえ法」は、カ音がタ音になっているような場合に試すとよい方法です。上歯の歯茎の方に上がっている舌先を舌圧子等でそっと押さえて下げてから、発音する方法です。ことばの教室の場合は、担当者が自分の指で自分の舌先を押さえて子どもに見せます。次に、同じように子どもにやってもらうという方法があります。
注意することは、子どもが吐きそうになったり、嫌そうだったりした場合はやめるということです。詳しくは、下記のサイトでご確認ください。
「キーワード法」+(ちょっぴりク音からの導き法)
「キーワード法」というのは、サ行音のときにお伝えした通りです。カ行音の中で、正しい音が出せる言葉がある場合に使えます。この方法は、他の音の発音練習でも使えます。
①正しく発音できる言葉があったら、それを繰り返し発音します。たとえば、「かめ」だったら、たくさん「かめ」を言います。
②少しずつ、「かめ」の「め」の部分を消していきます。
③カ音とタ音の文字カードをマッチングします。(カ音の意識付けです)
これらの発音練習を、ことばの教室では、絵カードを使ったり、タブレットを使ったりしながら、楽しく行うことがほとんどです。そのお子さんに合わせて行うためです。もちろん、トレーニング色が濃い方が合う場合は、そういう雰囲気で行います。
発音練習と並行して行う練習は、音の聞き分けです。たとえば、「カ音」が「タ音」になっている場合は、「カ音」と「タ音」を聞き分ける練習をします。
もし、「くま」がキーワードの単語だったら、ク音から練習するといいことが1つあります。それは、ク音にア音やオ音をつけると、カ音、コ音を導けるということです。音の足し算ですね。「ク+ア=カ」です。
ご家庭では
これらの練習は、ことばの教室の担当者にお任せした方がよいと思います。ご家庭では、たくさん正しいカ行音を耳から入れてあげてください。絵本の読み聞かせもいいですね。そして、言葉の「言い直し」はしないでくださいね。発音の獲得には個人差があります。お子さんの伸びる力を信じましょう。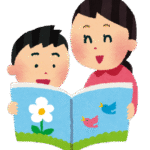
カ行音に効果的と思われるお口の体操
最後に、カ行音に効果的と思われるお口の体操をご紹介します。あくまでも、経験からの私見ですが、参考になさってください。授業は45分間あります。「お口の体操」をしなくても、発音練習はできます。でも、せっかくたっぷりと時間があるのですから、舌の筋力やコントロール力をつけるのはわるくないと思います。それに、「お口の体操」は、お口の準備運動のようなもの。これから、「発音練習するぞー」という動機づけになります。発音がうまくいかない日があっても、「お口の体操」で、たくさん子どもをほめることもできます。ほめると、子どもはもちろんうれしいですが、実はことばの教室担当者も心が弾んでうれしくなりますよ。
カ行音に効果的なお口の体操は、なんといっても奥舌を意識しやすい「うがい」です。
ガラガラうがい
うがいは、「舌の構えを教える方法」につながります。しかし、カ行音で苦戦しているお子さんは、ガラガラうがいも苦戦していることがあります。そのため、ガラガラうがいを嫌いにならないように、スモールステップでガラガラうがい練習を行うことが大切です。担当者や保護者の方は、「自分が苦手なことをやれ」と誰かに言われたときの気持ちをイメージしてくださいね。そうすれば、無理に進めることがどんなにトレーニングにマイナスか分かるはずです。
手順としては、水は少量から、顔の向きも少しずつ上にしていきましょう。最初と最後は、得意なぶくぶくうがいで、しっかり口周りを動かして、ぴゅーっと排水溝に口の中の水を出しましょう。
舌の出し入れ
舌を前後に巧みに動かすトレーニングです。舌の上にラムネやボーロをのせて、それを落とさないようにして、ゆっくりと舌の出し入れをします。最初は1つのせます。上手になったら2つ、3つと数を増やしていくといいですね。出し入れする回数を増やすのもいいでしょう。注意する点は、舌の左右の端っこは口角につけて、安定した舌の形で行うことです。舌の出し入れが済んだら、口の中のお菓子は、よく噛んで、しっかりと飲み込みましょう。そして、最後は虫歯にならないようにとうがいができますね。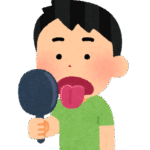
よく噛んで、飲み込む
口の中で食べ物を飲み込む一連の動きは、カ行音、ガ行音、ン音の舌の動きにつながります。だから、食事のときに、ゆっくりとよく噛んで、しっかりと飲み込むことが口の体操につながります。しっかりと飲み込こんでいれば、唇は閉じていて舌は上あごにつき奥歯を噛んでいると思います。
そのほかに、「せきばらいごっこ」「寝たふりをして、いびきかきごっこ」「あっかんべー」もいいですね。そして、あおむけに寝て、カ行音を発音することで、カ行音が出るときがあります。舌の位置がカ行音の位置になるからです。

ご家庭では
トレーニングではなく、楽しく取り組めるものがよいと思います。以下の記事を参考になさってください。「噛む」、「うがい」、「歯みがき」は基本です。
おうちでできるお口の体操 | ことばの教室(ことのはーゆゆ)
まとめ
いかがでしたか。カ行音を発音するときの舌の位置やそれに効果がありそうなお口の体操などがお分かりいただけたら幸いです。ことばの教室では、このほかに、音の聞き分けの練習等もして、自分でフィードバックする力も育てます。そうすることで、正しい発音が生活に広がっていきます。
繰り返しになりますが、正しい発音の獲得には個人差があります。気になる場合は、幼稚園や学校の先生に相談なさるとよいと思います。
さて、次回は「上手な断り方」について考えてみたいと思います。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。ことゆゆでした。